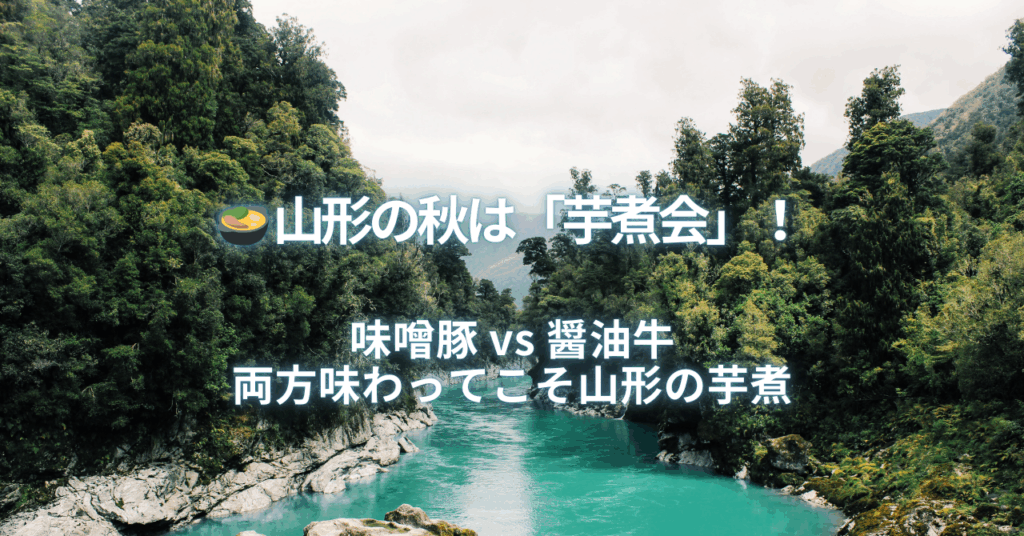河原や公園に集まり、大鍋で里芋を中心とした具材を煮込んでみんなで食べる行事です。家族や友人、会社の仲間が一堂に会して楽しむこの風習は、秋の風物詩として県民の心に根づいています。
そして芋煮会には、必ずといっていいほど盛り上がる話題があります。それが「味噌豚か?醤油牛か?」という味付けの違い。山形の人にとっては定番の“あるある”です。
芋煮会のはじまり
芋煮会のルーツには諸説ありますが、大きくは二つ。ひとつは江戸時代の最上川舟運文化、もうひとつは農作業の打ち上げとしての野外鍋です。
最上川は江戸時代、米や紅花を江戸や大阪に運ぶ重要な物流ルートでした。舟の出発や到着時に、船頭や荷主が川原で鍋をかこんで労をねぎらったと伝わります。また秋は稲刈りや収穫の時期であり、農作業の区切りに地域の人々が川原に集まり、里芋や身近な食材を煮て分かち合ったのです。川原は広くて薪や水が豊富に使える場所。そこから「芋煮会」の文化が定着していきました。
内陸の味:醤油×牛肉
山形市や村山地方など内陸部の芋煮は、醤油ベースに牛肉を合わせるのが基本です。
-
江戸時代から米沢藩では牛を「薬喰い」として食べる習慣があり、牛肉文化が根付いていたこと。
-
舟運で大阪・京都から伝わった醤油文化が組み合わさったこと。
こうして「醤油+牛肉+里芋」というシンプルで旨みのあるスタイルが広がり、今では内陸の芋煮の代名詞になっています。すっきりとした醤油味に牛の脂の甘さが溶け出し、ご飯にも合う味わいです。
庄内の味:味噌×豚肉
一方、日本海側の庄内(鶴岡・酒田)では味噌ベースに豚肉が定番です。
-
北前船による海運で、京都や北陸から味噌が大量に伝わったこと。
-
農家では豚を飼うのが一般的で、身近で安定したタンパク源だったこと。
濃厚な味噌の風味と豚肉の旨みが合わさり、寒さの厳しい庄内の人々にとって力強いごちそうになりました。こってりとした味わいは体を温め、冷めても美味しいのが特徴です。
なぜ味が分かれたのか?
「同じ山形県なのに、なぜここまで違うのか?」とよく聞かれます。その答えは、物流ルートと生活の違いにあります。
-
内陸部は最上川舟運で醤油や上方文化が入り、牛を飼う土壌があった → 牛肉と醤油の芋煮へ。
-
庄内地方は北前船で味噌文化が入り、農家で豚を育てやすかった → 豚肉と味噌の芋煮へ。
さらに、冬の暮らし方も影響しました。
-
内陸は大鍋で大量に作りやすく、あっさりした醤油味が重宝された。
-
庄内は保存性と栄養を重視し、濃い味噌味が選ばれた。
こうして、それぞれの地域が「自分たちの暮らしに合った芋煮」を育てていったのです。舟運と海運、牛と豚、醤油と味噌――この組み合わせの違いが、今の“二大芋煮”を生んだ背景といえるでしょう。
永遠の論争、でもどちらも正解
山形県民なら誰もが一度は「どっちが本物か?」で盛り上がった経験があります。
「牛醤油じゃないと芋煮じゃない!」という声もあれば、「いや、庄内は豚味噌が正統派!」という声も。どちらも熱い思いがあり、県民同士で笑いながら毎年のように論争が繰り返されます。
しかし、実際のところ どちらも正解。歴史と暮らしの違いがそれぞれの味を作り、山形の食文化を豊かにしてきたのです。論争すること自体が芋煮会の楽しみの一つであり、文化の深みを物語っています。
わたうさぎに泊まって芋煮会を楽しもう
鶴岡市にあるゲストハウス「わたうさぎ」では、庄内地方ならではの暮らしを体験できます。
近隣のお店で芋煮を味わったり、スーパーで「芋煮セット」を購入してわたうさぎのキッチンで手づくりするのもおすすめ。これなら内陸風も庄内風もどちらも楽しむことが可能です。
さらに、すぐ近くの赤川の河川敷で青空の下、家族や友人と一緒に芋煮会を開くこともできます。
宿泊者同士や地域の人との交流を通して、山形の芋煮文化をより深く楽しんでほしいです。
まとめ:両方味わってこそ山形の芋煮
芋煮会は、山形が誇る食と文化の結晶です。内陸の「醤油牛」、庄内の「味噌豚」、どちらも地域の歴史が作り上げた正統派の芋煮。
旅行で山形を訪れたなら、ぜひ両方を食べ比べてみてください。味の違いを楽しみながら、その背景にある歴史や暮らしを感じることで、芋煮会はただの料理ではなく、山形の文化体験そのものになります。
あなたは「味噌豚派」?それとも「醤油牛派」? コメントでぜひ教えてくださいね!
地元山形、地元鶴岡・地元庄内の魅力も発信しています。
最新の更新情報はインスタのストーリーズでお知らせしています。
インスタをフォローしてお待ちくださいね😊
いいね・シェアもうれしいです💕
関連記事