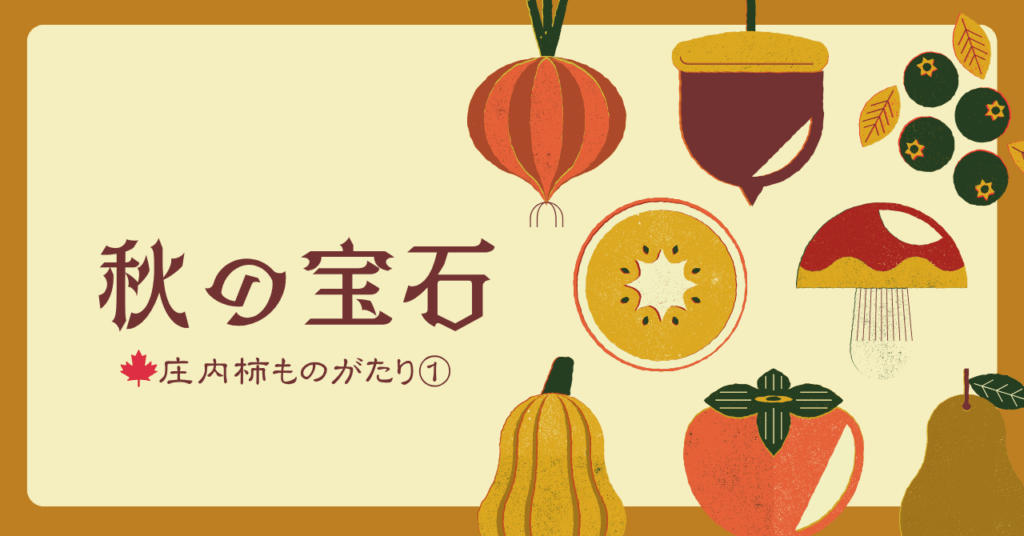「柿が好きなんじゃなくて、庄内柿が好きなんです。」
さちこさんはアツくそう話します。
そう言うと、みんなちょっと笑います。
でも気にしない!
さちこさんにとって“庄内柿”は秋のごほうび。
シーズンはほんの数週間。
気づいたら過ぎてしまうほど短いのに、その濃密な甘さが忘れられない。
だから、せめてもう少し長く味わいたくて、最近はドライフルーツにして楽しんでいます。
秋の光をたっぷり吸い込んだあのオレンジ色は、毎年ちゃんと心にしみるんですよね。
庄内柿という果実の正体
庄内柿の正体は「平核無(ひらたねなし)」という渋柿。
名前のとおり、種がなく、平べったい四角い形が特徴です。
生のままでは渋くて食べられませんが、「脱渋(だつじゅう)」という工程を経ると、一転してとろけるような甘さに変わる──
まるで魔法みたいな果物です。
明治の終わり頃、庄内にこの平核無が導入された当初は、「本当にこの寒い土地で甘くなるのか」と心配されたそう。
けれど、日本海からの風と昼夜の寒暖差、そして粘土質の豊かな土が、この柿にはぴったりだったんですね。
以来、庄内の秋を代表する果物として愛されてきました。
農家さんの手と、秋の短い戦い
庄内柿の収穫期は、10月中旬から11月上旬。
秋が深まり、山のてっぺんに初雪が見え始める頃です。
けれど、この短い期間が本当に大変。
台風の余波で落果したり、長雨で実が割れたり、朝霜で皮が傷んだり。
農家さんたちは空を見上げながら、毎日が緊張の連続です。
収穫のあとは“脱渋”という繊細な作業。
柿の渋みを取るために二酸化炭素やアルコールを使うのですが、温度や湿度、時間のわずかな違いで
味がまったく変わってしまうんです。
ベテランの農家さんは、柿を見ずとも“香りと音”で判断します。
箱を開けた瞬間にふわっと立つあの甘い香り、それが「ちょうどいいタイミング」の合図。
「柿は人を待ってくれないんだよ」
そう笑うおじいさんの手は、どの果実よりも日焼けしていて美しいのです✨
(さちこさんの偏愛が垣間見えます😆)
“脱渋”という小さな奇跡
柿の渋みの正体は「可溶性タンニン」。
そのままだと口の中がキュッとなるけれど、アルコールや炭酸ガスで不溶化させると、舌に感じなくなるという仕組み。
科学的に言えば簡単だけど、実際は気温や個体差、果実の呼吸によって微妙に変わる。
だからこそ、農家さんの感覚が欠かせません。
熟成の度合い、香り、果肉の張り──
それを“肌で読む”のが庄内の職人たち。
一瞬の気のゆるみで、甘みが抜けたり、逆に渋みが戻ることもある。
そんな“生きもの”を相手にしているから、彼らの仕事はどこか神聖にも見えるのです。
庄内柿と、ほかの柿たち
全国にはいろんな柿があります。
有名な富有柿は、はじめから甘くてコクが深い。
次郎柿は歯ごたえがあって、サクッとした食感が魅力。
筆柿や蜂屋柿は、干してからが本領発揮。
対して庄内柿は──
派手さはないけれど、すっきり上品な甘さ。
口に入れた瞬間、ぷるんとほどけて、あとにほんのり残るのは“静かな余韻”。
まるで庄内の人そのもの。
実直で、控えめで、でも芯が強い。
そんな土地柄が、この果実にそのまま映っている気がします。
短い旬、だからこそ特別
庄内柿が店頭に並ぶのは、ほんの2〜3週間ほど。
その後、気づけばすぐに初雪が降り、街の色もすっかり冬模様になります。
「あのオレンジ色が消えると、コートの季節が来た」
私は毎年そう感じます。
だからこそ、今年も逃さずに味わいたい。
手に取るその一粒が、一年のごほうびみたいに思えるのです。
そして、農家さんの手で磨かれた柿のひとつひとつに、重みや渋みやストーリーをさちこさんは感じるのです。
おわりに──また、来年の秋に。
庄内柿は、ただ甘い果物ではありません。
土地と人の手が生み出す“文化”であり、うつろいゆく季節の象徴でもあります。
食べ終えたあと、あの独特の甘さが喉の奥にふわりと残る。
それが、庄内の秋の記憶。
今年も無事に柿を食すことができる幸せをありがとう。
また来年もこの味に会えますように。
柿愛が止まらないさちこさんは、次回も柿の魅力を語る予定です。
次回は、庄内柿が持つ“女性の味方”としての力──
美と健康を整える秘密を、お届けします⭐️
今日の記事はここまで。
最新の更新情報はインスタグラムのストーリーズでお知らせしています。
フォローしてお待ちくださいね🥰
スキ・シェアもうれしいです❤️